はじめに
「毎月の税金や住民税、なんだかよく分からないまま引かれている…」
「もっと手取りが増えたらいいのに」
そんな風に感じたことはありませんか?
実は、ふるさと納税という仕組みを使うだけで、税金の一部を節約しながらお得な返礼品をもらうことができるんです。
僕も最初は「ふるさと納税って難しそう…」と思っていましたが、実際にやってみるとネットショッピングとほとんど同じ感覚。お米やお肉など生活に役立つものが届いて、しかも翌年の税金も安くなりました。
この記事では、新社会人でも簡単にできる「ふるさと納税の始め方」 をわかりやすく解説します。
さらに、失敗しないための注意点やおすすめの利用方法も紹介しているので、ぜひ最後までチェックしてみてください!
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付をすると、翌年の税金が控除される制度のことです。
さらに、寄付をしたお礼として「返礼品(お米・お肉・果物・家電など)」がもらえるのが大きな特徴!
たとえば…
- 30,000円分を寄付すると、その分の税金が翌年差し引かれる
- 実質自己負担は2,000円だけ
- それなのに寄付先から豪華な返礼品が届く
という仕組みです。
簡単に言えば、税金の前払い+お礼の品つきって感じです!
税金が安くなる仕組み
ふるさと納税で寄付したお金は、翌年の住民税や所得税から控除(差し引き)されます。
ただし、控除には「上限額」があるので、年収や家族構成によって最大いくらまで寄付できるかは人によって違います。
✅例えば「年収300万円・独身」の場合、寄付の上限額はだいたい3万円前後。
この範囲で寄付をすれば、翌年の税金が減って返礼品ももらえる、というわけです。
返礼品がもらえる理由
もともと税金は「自分が住んでいる自治体」に納めますよね。
でもふるさと納税は「住んでいない自治体にも寄付できる」仕組みなので、自治体は「うちに寄付してもらえるように!」とお礼の品を用意しているんです。
つまり、ふるさと納税は
- 自治体 → 寄付が集まる
- あなた → 返礼品+税金控除でお得
という Win-Winの制度 なんです!
新社会人がふるさと納税をやるメリット
社会人になると、アルバイトのときよりも収入が増え、その分「税金」もしっかり取られるようになります。
ふるさと納税は、そんな新社会人にこそメリットが大きい制度なんです。
節税しながらお得
ふるさと納税は「実質2,000円の負担」でいろんな返礼品がもらえます。
普段ならそのまま引かれていく税金を、自分の意思でコントロールできるのがポイント。
- 2,000円でお米10kg
- 2,000円でブランド牛
- 2,000円で人気のスイーツ
など、うまく活用すれば 食費や生活費を浮かせる節約術 にもなるんです。
初めてでも簡単にできる
「確定申告が難しそう…」と思うかもしれませんが、実はとてもシンプル。
多くの人は ワンストップ特例制度 を使えば、寄付後に届く申請書を郵送するだけでOK。
ネットショッピング感覚で返礼品を選んで、支払いもクレジットカードやPayPayなどが使えるから、思ったよりも簡単に始められます。
好きな地域を応援できる
「生まれ育った地元に恩返ししたい」
「旅行で行ったあの町を応援したい」
そんな気持ちで寄付をすることもできます。
単なる節税だけでなく、地域の応援につながるのもふるさと納税の魅力です。
新社会人にとっては、
- 節約になる
- 簡単にできる
- 社会貢献にもつながる
という3つのメリットがあるから、早めに始めるのがおすすめです。
ふるさと納税のやり方【初心者向けステップ】
「やってみたいけど、難しそう…」って思うかもしれません。
でも、ふるさと納税はネットショッピングとほとんど同じ感覚でできるんです。
ここでは初心者でも迷わないように、シンプルにステップをまとめました。
① 上限額を調べる
まずは「自分がいくらまで寄付できるか」を確認しましょう。
ふるさと納税には 控除の上限額 があるので、それを超えるとお得になりません。
📝調べ方
- ふるさと納税サイト(例:楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび など)にある「かんたんシミュレーション」で年収・家族構成を入力するだけ
② 返礼品を選んで寄付する
上限額がわかったら、好きな返礼品を選びます。
お米、肉、魚、果物、スイーツ、日用品まで種類はさまざま。
💡ポイント
- 「普段買っているもの」を選ぶと食費や生活費の節約になる
- 「ちょっと贅沢」な返礼品を選べばご褒美気分も味わえる
選んだら、カートに入れてクレジットカードや電子決済で支払い。ネットショッピングと同じ流れです。
③ ワンストップ特例制度を利用する
寄付が終わると、自治体から「寄付金受領証明書」と「申請書」が届きます。
確定申告が必要ない人(会社員の多く)は、この申請書を郵送するだけで手続き完了!
❗注意点
- ワンストップ特例制度は「寄付先が5自治体まで」
- 6自治体以上に寄付すると確定申告が必要になる
④ 翌年の税金が安くなる
寄付をした翌年の住民税・所得税から控除されます。
これで「実質2,000円の負担」で豪華な返礼品が楽しめるわけです。
こうしてみると、やることはたったの 4ステップ。
初心者でもすぐに取り組めるのがふるさと納税の魅力です。
おすすめの返礼品ジャンル
ふるさと納税といえば「お肉」「果物」などが定番ですが、20代の新社会人におすすめなのは 生活必需品系 です。
① ティッシュ・トイレットペーパー(生活消耗品)
僕が特におすすめするのが ティッシュとトイレットペーパーのセット。
一度頼むだけで、2人暮らしでも半年くらいは買い足す必要がなくなりました!
メリット
- 毎月のドラッグストアでの買い物が減る
- 「トイレットペーパー切れた!」って焦ることがない
- 値上がりの影響を受けにくい
② お米(主食系)
スーパーで買うと持ち運びが重いお米も、ふるさと納税なら自宅に届くので便利。
定期便にすれば数か月に一度届くので、買い忘れ防止にもなります。
③ お肉・魚(ご褒美グルメ)
普段はちょっと高くて買わないようなお肉や海鮮を、実質2,000円で楽しめます。
友達を呼んで鍋パーティーするときなんかにもおすすめです。
④ 日用品(洗剤・調味料など)
まとめ買いすると地味に出費がかさむものも、返礼品でまかなえます。
僕の知り合いは「洗濯洗剤」をふるさと納税で頼んで、1年分ほぼ買わなくて済んだそうです。
⑤ 5自治体の寄付制限と僕の選び方
ちなみに、ふるさと納税は年間で5つの自治体までしか寄付先を選べません。
僕の場合は、
- 4つは生活に必要な消耗品や日用品(ティッシュ・トイレットペーパー・お米など)
- 1つはちょっと贅沢なグルメやスイーツ
というバランスで選んでいます。
こうすることで、普段の生活費を節約しつつ、1つは「ご褒美枠」として楽しめるので無理なく続けられます!
💡 ポイント
- 実用的なもの+ちょっと贅沢なものを組み合わせる
- 生活費の節約につながる返礼品は新社会人に特におすすめ
ふるさと納税で失敗しないための注意点
ふるさと納税はお得な制度ですが、知らないままやると損をしてしまうこともあります。
新社会人に特に押さえておいてほしいポイントをまとめました。
① 寄付の上限額を確認する
ふるさと納税には 控除の上限額 があり、超えると寄付金が全額控除されません。
- 年収や家族構成によって上限が変わる
- まずは各ふるさと納税サイトのシミュレーションで確認してから寄付する
② ワンストップ特例は5自治体まで
ワンストップ特例制度を使う場合、年間5自治体までが上限です。
- 6つ以上の自治体に寄付すると、確定申告が必要になる
- 僕の場合は、4つは生活消耗品や日用品、1つは贅沢品として使い分けています
③ 申請や手続きを忘れない
寄付後に届く「申請書」を郵送するか、確定申告で手続きを行う必要があります。
- ワンストップ特例の場合:書類を提出しないと控除が適用されない
- 確定申告の場合:期限内に申告しないと控除されない
④ 年末ギリギリの寄付は注意
- 年末にまとめて寄付すると、書類の到着や手続きが間に合わない可能性がある
- 余裕を持って11月くらいまでに寄付するのがおすすめ
⑤ 返礼品の到着時期を確認する
- お米や肉など一部の返礼品は、寄付後すぐに届くわけではありません
- 到着時期が指定されているものや、季節限定の商品もあるので、注文前に確認しておく
💡 ポイント
- 上限額・自治体数・手続きの3つを守れば、初心者でも安心してふるさと納税ができる
- 僕も最初は「ややこしい」と思ったけど、このルールさえ押さえておけば簡単に活用できます
まとめ
ふるさと納税は、節税+お得な返礼品 が手に入る、新社会人にとって非常に便利な制度です。
- 自分の住んでいる自治体以外にも寄付できる
- 寄付した金額のほとんどが翌年の税金から控除される
- 返礼品として生活必需品やちょっとした贅沢品がもらえる
初心者でも簡単に始められるので、まずは少額からチャレンジしてみるのがおすすめです。
僕の場合は、生活消耗品や日用品を4つ、贅沢品を1つ選ぶバランスで寄付しています。
ふるさと納税を上手に活用すれば、生活費を節約しつつ、日々の生活にちょっとした楽しみも加えられます。
ぜひ、あなたも自分に合った返礼品を選んで、賢く節税&お得ライフを始めてみてください!
【関連記事】

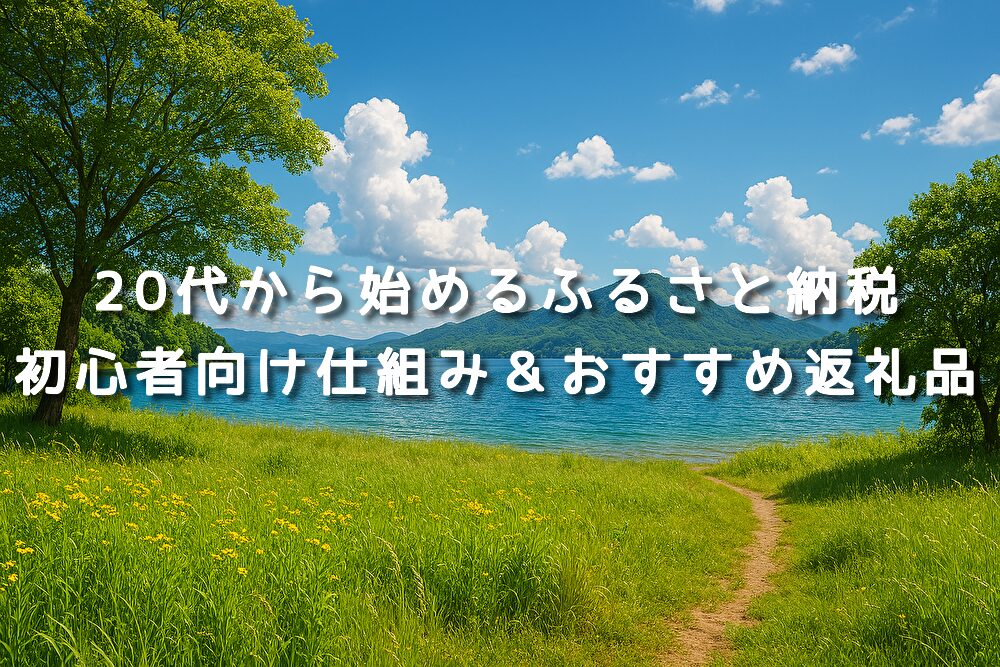

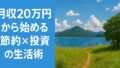
コメント